【屁の話】オナラが出まくる!オナラがクサい!何が原因なのか徹底調査!!
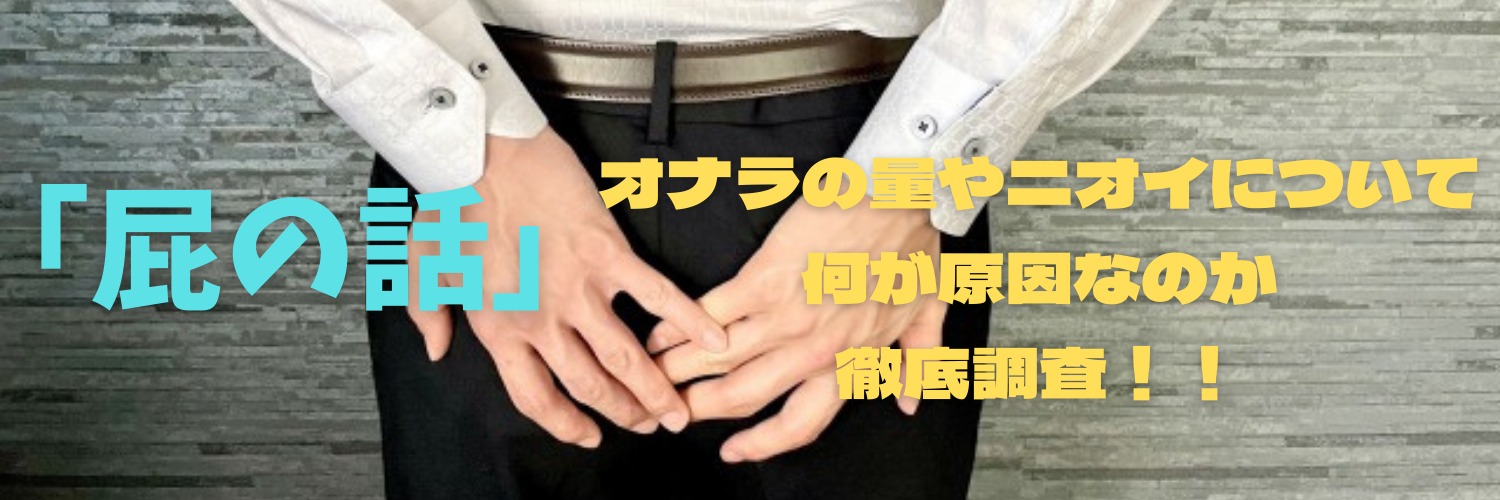
こんにちは!!
今回は私自身の悩みでもある「屁の話」ついて徹底調査してきました。
この悩みって男女問わずとも、結構深刻な悩みだったりしませんか?
日常生活で「オナラの回数が多い」「オナラがクサい」これって大丈夫なのか?
っと心配になってきたりもします。
っという事で今回はオナラについて、徹底調査してきたので報告させて頂きます!!
あなたも是非とも参考にして見て下さいね(*^-^*)
もくじ
オナラの原因

まずは、オナラがどのようにして作られるのか説明しましょう。
基本的には、口や鼻から飲み込んだ空気と腸内細菌が食物を消化する過程で発生したガスが「オナラ」として排泄されます。
オナラ自体は基本的には無臭で、その成分は「窒素・酸素・水素・二酸化炭素・メタン」などです。
オナラは1日に200~2000ml程度が作られ、成人の1日のオナラの平均回数は約7〜20回と言われています。
もちろん、個人差がありますのでおおよその目安として考えてください。
では、オナラの多さや匂いなどの原因にはどのようなものがあるか見ていきましょう。
- 早食い・食事中の空気の飲み込み
- 便秘
- ストレス
早食い・食事中の空気の飲み込み
仕事などで忙しい時は、なかなか食事をゆっくり食べれないケースが多いですよね。
そのために早食いをしてしまうと、一緒に空気を多く取り込んでしまいます。
その結果、排出されるオナラも多くなってしまうのです。
また早食いはオナラの量が増えてしまうだけでなく、消化にも負担がかかりやすくなってしまいます。
オナラの量が多いと感じる人は、一度自分の食事の食べ方を振り返ってみましょう。
便秘
男性でも、便秘で悩んでいるという人は多いですよね。
便は出ないのに、オナラがたくさん出てしかも臭いという場合もあります。
腸内環境が悪く便秘になると、排出されない便が腸内でさらに悪玉菌を増加させてしまう要因になり、悪循環が起こります。
そうすると、ニオイのあるオナラが発生しやすくなってしまうのです。
ストレス
近年の研究で、腸と脳はつながりがあることがわかったそうです。
確かに緊張して強いストレスがかかると、とたんにお腹が痛くなりトイレに駆け込むという人も多いのではないでしょうか。
精神的にストレスを感じると、唾を飲み込む回数が多くなります。
その時に空気も一緒に取り込んでしまうため、ストレスを感じるとお腹が張ってオナラが多くなってしまうこと事があるそうです。
またストレスがたまると食欲が低下してしまい、逆にファストフードなどをドカ食いしてしまう場合もあります。
そうなると腸内環境のバランスが崩れ、腸の働きも低下してしまうのです。
そして、腸内環境が悪化すると脳にも影響が出てしまい、ますます悪循環が生まれます。
腸の状態は、単純にオナラだけでなくメンタルにも影響を与えているのです。
体調不良や病気のサインの場合も?

オナラが明らかに臭いと感じるときは、次のような体調不良や病気のリスクも考えられます。
不安に感じたら早めに専門医の診断を仰ぎ、必要な検査を受けてください。
- 慢性胃炎
- 大腸がん
慢性胃炎
ピロリ菌感染や薬の副作用またストレスなどで胃炎になり、胃腸の働きが弱まる症状です。
腹部膨張感や胃もたれなどの症状を併発している場合は、オナラの臭いはかなりきつくなりがちです。
大腸がん
大腸がんが悪化すると、食べ物が腐ったような独特の臭いのオナラが出ると言われます。
また、大腸がんの場合は便に血が混じっていることもあります。
これらの症状は大腸がんのサインの可能性もあるので、気づいた段階ですぐ病院へ行くようにしてください。
オナラの症状

主にオナラに関して気になるのは、「におい」「たくさん出る」この2点ではないでしょうか。
そこで、ここではその原因と対策について解説します。
におい
においの原因としては、肉・玉子などの動物性たんぱく質過剰摂取が挙げられます。
肉や卵など動物性たんぱく質を多く含む食品を過剰に摂取すると、これを栄養源としている悪玉菌が増えて臭いオナラを作り出します。
対策としては、肉や卵などの摂取量を見直すことです。
肉や卵には体づくりに必要なアミノ酸やビタミン・ミネラルなどが含まれています。
なので食べるのをやめるのではなく、自分に合った量を見つけていきましょう。
たくさん出る
オナラがよく出る原因として、食物繊維を摂りすぎること(とくに芋類の過剰な摂取)が挙げられます。
食物繊維は適度に摂れば便通を整えてくれたり、さまざまな疾患の発生リスクを下げてくれたりと優秀な働きをしてくれます。
しかし食物繊維を摂りすぎると腸内でガスを発生させやすくなったり、逆に便秘を悪化させてしまいオナラの量が多くなったりニオイがきつくなったりすることがあります。
対策としては、食物繊維の量を調整することや、水溶性食物繊維の摂取を意識することです。
食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。
不溶性食物繊維を多く含む食材には、穀類・野菜・きのこ・豆類・根菜類などです。
水溶性食物繊維を多く含む食材は、海藻類・こんにゃく・大麦などがあります。
我慢したオナラは何処へ?

普段の生活の中で、オナラを出すのを我慢してやり過ごすことになる状況はけっこうありますよね。
そんな時、我慢したオナラはどこにいくのでしょうか?
基本的には、身体の中に吸収されてしまうようです。
普通は大腸内、量が多い時は小腸内までさかのぼって血液中に取り込まれ、呼吸やゲップとして出ていきます。
オナラを我慢することで、健康への影響はありません。
しかし臭いのもとになる物質が体内をめぐることで、結果として体臭や口臭がきつくなるといったことは十分考えられます。
オナラをがまんしないというのはなかなか難しいですが、できるだけこまめにお手洗いにいくなどしたいですね。
オナラの対処法として

ここまで、オナラの正体やニオイの原因についてお話してきました。
では、日常生活の中で出来るオナラ対策には、どのようなものがあるかお話していきましょう。
- 出来る限り溜めない・我慢しない
- 食生活の改善
出来る限り溜めない・我慢しない
まず出来るだけ、オナラを不必要に腸内にためないようにしたいものです。
オナラが腸内にたまると、周辺臓器をも圧迫してしまいます。
さらに、悪玉菌が生み出す臭いニオイの元の物質には、体に吸収されると有害なものがあります。
また、臭いニオイ成分の硫化水素などが吸収しきれず残るので、我慢した後で出るおならは更に臭くなります。
我慢などで腸内にたまったオナラは、有害物質とともに腸管から吸収されて血液中に溶け込み全身へと運ばれます。
血液中に溶け込んだオナラは皮膚や呼気から体外へ排出されるので、体臭や口臭がきつくなることもあります。
食生活の改善
普段の食生活を改善する事も、オナラ対策には非常に有効です。
- タンパク質やニオイが強い食品の摂りすぎを控える
- 悪玉菌の数を増やさない様にする
タンパク質やニオイが強い食品の摂りすぎを控える
普段の食生活の中で、なるべくお肉やニラ・ネギなどの量を減らしましょう。
代わりに食物繊維や炭水化物を多く摂るようにすると良いそうです。
悪玉菌の数を増やさないようにする
日ごろから腸活を心がけ腸内の善玉菌を増やすように、ヨーグルト・オリゴ糖などを積極的に摂るようにしましょう。
また、整腸薬を活用することも、一つの手段です。
便が腸内に長く留まらないようにする
便秘になると、腸内での便の滞留時間が長くなります。
そのため腸内の悪玉菌によるタンパク質等の分解が進み、臭いニオイがする物質の産出量が増えてしまいます。
血中への有害成分の移行や、無臭のガスの産出増にもつながりますから、おなら対策として便秘の防止や解消は大切です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、オナラの原因や対処法などについてお話させて頂きました。
もちろん個人差もありますので、全ての方法で効果が出るとは限りません。
自分自身で実際に試してみて、効果のあるものはどれか探してみてください(*^▽^*)




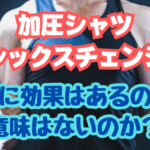


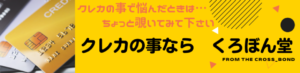
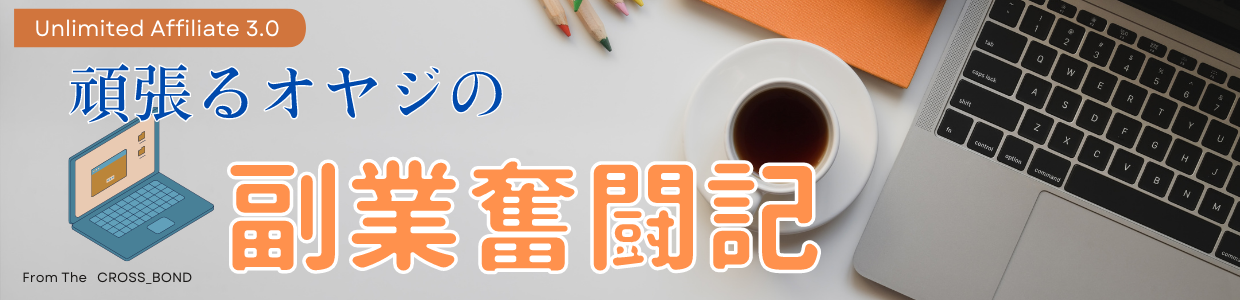

コメントフォーム